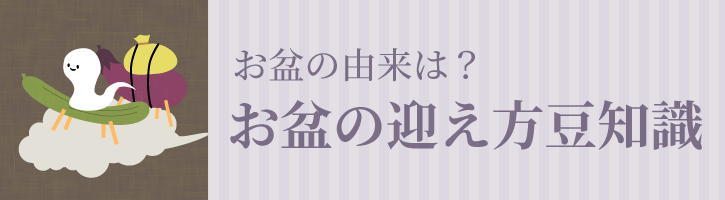お盆を前に知っておきたい!お墓参りの豆知識
- 暮らし
更新日:2019年08月10日
亡くなった人の冥福を祈るとともに、家族が無事に暮らしていることを報告し、ご先祖さまに感謝する「お墓参り」は日本人の大切な習慣です。今回は意外と知らないお墓参りの基礎知識とマナーを紹介します。
お墓参りの時期やタイミングはいつ?

お墓参りはいつしてもいいのですが、主な時期は下記のような場合です。先祖を供養し、敬う気持ちを大切にするためにもできるだけ毎年お墓参りを行いましょう。
1. 命日
故人が亡くなった月日である祥月命日と、亡くなった日にあたる毎月一回の月命日とがあります。
祥月命日には、法事・法要が営まれるほか、お墓参りをすることが多いようです。月命日には、自宅で仏壇にお花を供えて供養してもいいでしょう。
2. お盆
お盆とは先祖の霊が年に一度あの世から帰って来るという日本古来の信仰に基づく行事です。地域によって異なりますが、東京など都市部は7月13日~16日、地方では8月13日~16日の4日間。
3. お彼岸
年に2回、春のお彼岸と、秋のお彼岸の時期があり、春分・秋分の日を中日(ちゅうにち)とし、前後3日を合わせた7日間をいいます。年度によって春分・秋分の日は異なりますが、春分の日は、3月20日または21日頃。秋分の日は、9月23日頃です。
お墓参りの手順

1. 墓地の掃除
周りをほうきできれいに掃き、枯れた花や雑草などを取り除きます。そして墓石に水をかけ、スポンジや柔らかいたわしを用いて汚れを落とします。線香台、水鉢、花立も歯ブラシなどで汚れを落としていきます。
2. お供え
花立てに水を入れお花を飾ります。 そして故人の好物だった菓子・果物などをお供えします。お供え物は持参した器や半紙の上に置くといいでしょう。
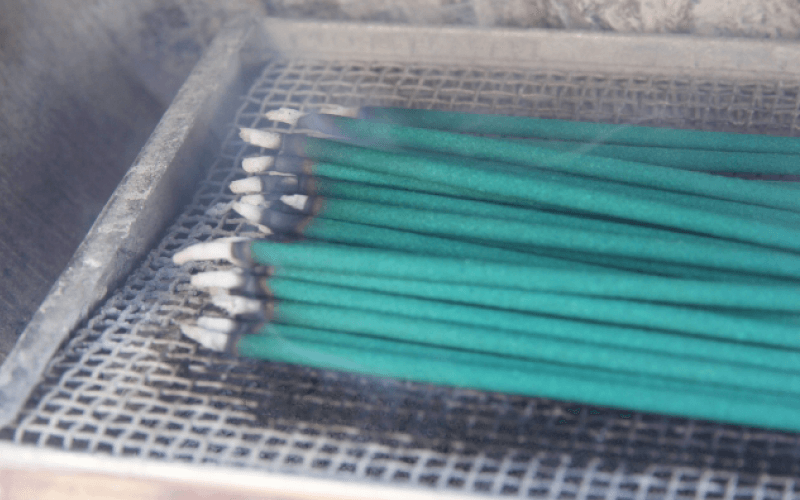
3. 焼香
ロウソクに火を灯し、束のまま線香に火をつけましょう。火はくれぐれも口で吹いて消さないように、手であおいで消します。そして人数分に分けてお供えするのが一般的です。
お参りの順番は故人と縁の深い者からとなります。
4. 墓石にお水をかけて合掌
墓石にてっぺんからたっぷりと水をかけて清めます。
(仏教の教えでは、死後の世界の1つに「餓鬼道」があり、お墓にかけられた水しか飲めない餓鬼への施し・慈悲の意味があります。)
そしてしゃがんで両手を合わせ、先祖や故人の冥福を祈り、近況の報告をします。
家族で参拝する時は故人と縁の深い者からとなります。

5. 後片付けもしっかりと
お供えの食べ物はカラスや野生動物が食べ散らかすので持ち帰るか、お供え物をご先祖様と分かち合うという理念から、その場でみんなでいただきましょう。お線香は安全のために燃やしきります。
※地方の習慣や宗派によってお墓参りの作法は異なり「これが絶対」というものはありません。
ただ最も大切なのはご先祖様を想う気持ちで、決まった時期だけでなく、気がついたときにお墓参りに行くようにしたいものです。毎日の生活の中で頻繁に行くのは難しいかもしれませんが、年に数回は家族そろってお墓参りできたらいいですね。
お盆に関する意外と知らない豆知識
おはぎとぼたもちの違い

お彼岸の供え物には、おはぎとぼたもちがつき物ですが、いったいどう違うのか知っていますか?
こしあん、粒あんの違い?米粒がのこっているかどうか?
実はおはぎとぼたもちは基本的に同じもので、違うのは食べる時期だけなのです。
「ぼたもち」はもともと「牡丹(ぼたん)もち」、「おはぎ」は「萩のもち」であったといわれます。ぼたもちは、牡丹の季節、春のお彼岸に食べるもので、おはぎは、萩の季節、秋のお彼岸に食べるものとされていたそうです。
今では一年中売られているので混同されてしますが本来はそのような意味があります。
盆踊りの由来って?

阿波踊りや郡上踊りなど全国各地で行われている盆踊り。本来はお盆にかえってきた御先祖様の魂を慰め、鎮める行事なのです。
盆踊りの晩(旧暦7月15日)に踊り、死者の魂を送り出す大切なものという意味があったのですが、現在は日にちにはこだわらず娯楽としての楽しみが一般化しています。
関連ページ
※この記事は2017年7月12日の公開後、追記・修正をして2019年8月10日に改めて公開しました。